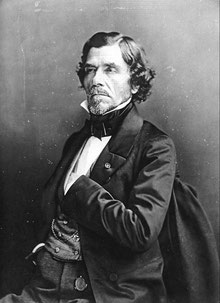ゲルニカ / Guernica
世界で最も有名なピカソの反戦芸術
概要
| 作者 | パブロ・ピカソ |
| 制作年 | 1937年 |
| メディウム | 油彩、キャンバス |
| サイズ | 349 cm × 777 cm |
| コレクション | ソフィア王妃芸術センター |
《ゲルニカ》は、1937年6月に完成したパブロ・ピカソによる壁画サイズの油彩作品。縦349cm×横777cm。スペインのソフィア王妃芸術センターが所蔵している。
《ゲルニカ》は、スペイン市民戦争に介入したナチスドイツやイタリア軍が、スペイン・バスク地方にある村ゲルニカの無差別爆撃した出来事を主題とした作品。
多数の美術批評家から、美術史において最も力強い反戦絵画芸術の1つとして評価されており、内戦による暴力や混沌に巻き込まれて苦しむ人々の姿を描いている。
作品内で際立っているのは、血相を変えた馬、牛、火の表現。絵画全体は白と黒と灰色のみの一面モノクロームとなっている。
1937年のパリ万国博覧会で展示されたあと、世界中を巡回。会場に設置された《ゲルニカ》は当初、注目を集めなかった。それどころか依頼主である共和国政府の一部の政治家から「反社会的で馬鹿げた絵画である」と非難を浴びた。
万博終了後、作品はノルウェーやイギリスといったヨーロッパを巡回。巡回で得られた資金はスペイン市民戦争の被害救済資金として活用された。
《ゲルニカ》が本格的に注目をあつめるようになったのは第2次世界大戦以降である。ゲルニカは世界中から喝采を浴び、結果として世界中へスペイン市民戦争に対して注目を集める貢献を果たした。
重要ポイント
- 美術史において最も有名な反戦絵画
- スペイン内戦時の暴力や混沌に苦しむ人々を描いている
- 最初は評価されず、第二次世界大戦後に再評価
制作概要
1937年1月、スペイン共和国政府は、ピカソにパリで開催されるパリ万国博覧会 (1937年)のスペイン館へ展示するための絵画制作を依頼する。当時、ピカソはパリに住んでおり、プラド美術館の亡命名誉館長職に就いていた。
ピカソが最後にスペインに立ち寄ったのは1934年で、以後フランコ独裁が確立してからは一度もスペイン戻ることはなかった。
「ゲルニカ」の初期スケッチは、1937年1月から4月後半にかけてスタジオで丹念に行われた。しかし、4月26日にゲルニカ空襲が発生。この事件を詩人のフアン・ラレアはピカソに主題にするようアドバイスをすると、ピカソはそれまで予定していたプロジェクト(フランコの夢と嘘)を中止し、「ゲルニカ」制作のためのスケッチに取り組み始めた。
1937年5月1日に制作を開始。6月4日に完了。写真家で当時のピカソの愛人ドラ・マールは、1936年からピカソの「ゲルニカ」制作に立ち会った唯一の人物で、当時のピカソの制作の様子を多数撮影している。
これまで、ピカソは作品制作中にスタジオに人を立ち入らせることはほとんどなかったが、「ゲルニカ」制作時は影響力のある人物であれば、積極的に製作中のスタジオに案内し、作品経過を公開した。理由は、作品を見てもらったほうが反ファシストに対して同情的になると信じていたためである。

ゲルニカ爆撃と人類の核心
ゲルニカはスペインのバスク州ビスカヤ県にある町。スペイン市民戦争時における共和党軍の北部拠点であり、またバスク文化の中心地として重要視されていた。
共和党軍はさまざまな派閥(共産主義者、社会主義者、アナーキストなど)から構成されており、それぞれ最終目標とするところは異なっていたものの、フランコ将軍率いる保守派に反対という立場で共通の目標を抱いていた。
保守派は、法律、秩序、カトリックの伝統的な価値に基いて共和党以前のスペインに回帰しようとしていた。
爆撃対象となったゲルニカは、当時のスペイン内戦の前線から10キロ離れた場所に位置し、またビルバオの町と前線の中間にあり、共和国軍のビルバオへの退却とフランコ軍のビルバオへの進軍の通過地点だった。
当時のドイツの空軍の規定では、輸送ルートや軍隊の移動ルートとなる地域は合法的に軍事標的と定められており、ドイツにおいてゲルニカは共和党の攻撃目標の要件を満たしていた。
ドイツ軍人ヴォルフラム・フォン・リヒトホーフェンの日記の1937年4月26日の日記で「4月25日にマルキナから退却する際に敗残兵となった共和国軍の多くは、戦線から10キロ離れた場所にあるゲルニカへ向かった。
K88戦闘機はここを通過する必要がある敵兵を停止させ、また混乱させるためにゲルニカを攻撃目標に定めた。」と書いている。
しかし、ゲルニカにおける重要な軍事標的は、本来ならば郊外にある軍需製品を製造する工場のはずだが、その工場は爆撃を受けなかった。また、共和党軍として戦うために、町の男性の大半はいなかったため、爆撃時の町はおもに女性と子どもたちによって占められていた。
ドイツ空軍の攻撃規定と食い違いがあるため、ゲルニカ爆撃の動機は共和国軍への威嚇・恫喝だとみなされている。 はっきりと保守派には、伝統的なバスク文化や無実な市民から成り立つ町に対して彼らの軍事力を誇示することによって、共和党軍や民間人たちの士気をくじこうとする意図があった。
当時のゲルニカ人口構成比は、ピカソの「ゲルニカ」の絵に反映されている。女性と子どもはゲルニカの無垢性のイメージをそのまま反映したものであるという。また女性と子どもはピカソにおいて人類の完璧さを表すことがある。
その女性と子どもへの暴力行為は、ピカソの視点から見ると、人類の核心へ向けられている。人類の核心とは画面中央したに描かれた壊れた剣と花である。

1937年4月30日付けの記事によれば
「最初のドイツ・ユンカース飛行団がゲルニカ到着すると、すでに煙が巻き上がっており、誰も橋、道、郊外を目標とせず町の中心に向かって無差別爆撃を繰り返した。250キロ爆弾や焼夷弾が家屋や水道管を破壊し、この爆撃で焼夷弾の影響が広まった。当時住民の多くは休暇で町から離れており、残りの大部分も爆撃が始まるとすぐに町を去った。避難所に非難した少数の人が亡くなった。」
バスク地域の共和国軍に同情を示す『Time』記者のジョージ・ステラは、ゲルニカ爆撃を国際的に紹介し続け、それがピカソの作品に注目を集めるきっかけとなったが、ステラは4月28日付けの『Time』と『The New York Times』、29日付けの『L'Humanité』で以下のように書いている。
「バスクの古都でありバスク文化の中心であるゲルニカは、昨日の午後、反乱軍の襲撃によって完全に破壊された。線の背後にあったこの開かれた町への爆撃は3時間ほど行われ、そのとき、3種類のドイツの爆撃機が飛来し、1000ポンドの爆弾を町に落とした。」
ほかの記事では、爆撃の当日は定期市が開催されていたこともあり、町の住民は市の中心に多く集まってたという。爆撃が始まったとき、既に橋が壊されて逃げられず多大な犠牲者を出したと報告している。
第二次世界大戦時のナチ占領下にあったパリにピカソが住んでいたとき、あるドイツ役人がピカソのアパートで「ゲルニカ」作品の写真を見て、「これはお前が描いたのか?」と質問されたとき、ピカソは「ちがう、お前たちがやった(空爆)」と答えたという。

絵の構成
絵の場面は部屋の中であり、画面左端が絵画の開始位置となる。
左端には死んだ子どもを抱えて悲しんでいる女性が描かれており、その女性の上には、目を細めた牛が描かれている。
画面中央には槍を突き刺されて苦しんでいる馬が描かれ、下には死んで解体された兵士が横たわっている。馬の顔の横にある大きな穴の空いた傷は、この絵のポイントである。切断された兵士の右手には壊れた剣と花があり、左手のひらにはキリストの傷跡と思われる思われる殉教の象徴が描かれている。馬の頭にある電球は邪悪な光を放っており、爆撃を連想させる。机の上の鳥は精霊や平和の象徴であるとされている。
馬の右上には、眼前で起きた出来事に恐怖に怯える女性の顔が描かれている。彼女は手にランプを持ち、窓から部屋を覗き込んで、現場の惨状を目の当たりにして驚いているように見える。ランプは希望の象徴だが、そのランプは不気味な電球のすぐ近くに対象的に置かれている。
右から畏敬の念を浮かべた女性が、浮遊する女性の顔の下から中央上に向かって顔を伸ばし、彼女の視線の先はちょうどランプと電球へ向かっている。右端には、日につままれて恐怖の顔を浮かべ腕を上げた女性が描かれている。彼女の右手は飛行機の形をしていることから爆撃の被害であることがわかる。
右端のドアは開いているので、絵画の終わりであることを意味している。


ゲルニカの解釈
ゲルニカの解釈は多様であり、正しい解釈はない。
美術史家のパトリシア・フォーリングは「牛と馬、ともにスペイン文化を象徴する重要なキャラクターである。ピカソはきっと自身を牛や馬に投影し、さまざまな役割を演じているのだろう。牛と馬の具体的な意味についてはピカソのこれまでの作品を通じてさまざまな表現がなされてきた。」と批評している。
ゲルニカについてピカソは質問されたときこう答えている。
「牡牛は牡牛だ。馬は馬だ。・・・もし私の絵のに何か意味をもたせようとするなら、それは時として正しいかもしれないが、私自身は意味を持たせようとはしていない。君らが思う考えや結論は私も考えつくことだが、渡しの場合は、それは本能的に、そして無意識の表出だ。私は絵のために絵を描くのであり、物があるがままに物を描くのだ。」
パリ万博のために作成した物語シリーズ「フランコの夢と嘘」においてピカソは、最初フランコを食い散らす馬として表現し、のちに怒り狂った牛(共和国軍やピカソ)と戦う馬として描いていた。この絵はゲルニカ爆撃前に描かれており、その後さらに4つのパネルが追加され、そのうち3つはゲルニカの絵画に直接関連している。
学者のビバリー・レイによれば、以下に並べた解釈リストが、美術批評家たちの共通要素とされている。
- 身体の形状や姿勢は反発を示している。
- 黒、白、グレーの塗料を使用していることから、ピカソの憂鬱な気分が反映されており、また苦しみや混沌を表現している。
- 炎上する建物や崩壊した壁は、ゲルニカの破壊を表すだけでなく内戦の破壊的な力をも表現している。
- 絵画にコラージュ的に使われている新聞紙はピカソがゲルニカ爆撃の事件をどのようにしったかを反映している。
- 電球は太陽を表している。
- 絵の下部に中央に描かれている壊れた剣は人類の敗北を示している。
アレハンドロ・エスカロナはこのように述べている。「混沌や虐殺は閉鎖された場所で発生しており、この悪夢のような場から逃げ出す方法はない。しかしながら、中央にゲルニカ事件を報じる新聞紙が貼られていることから分かるように、戦争の悲惨なイメージが現代世界では、メディアを通じて生き生きとして高解像度でリビングルームに映し出される。」
ドラ・マールやマリー=テレーズの肖像
「泣く女」は、ドラのポートレイトであると同時に、同年に制作された「ゲルニカ」の後継作であることも重要である。「泣く女」と「ゲルニカ」は互換性のある作品で、ピカソは空爆の被害を受けて悲劇的に絶叫する人々の姿とドラ・マールをはじめ泣く女とをダブル・イメージで描いていた。
実際に、ゲルニカ作品で右端に描かれている絶叫している女性はドラ・マールであり、左端で子どもを抱えている女性はマリー=テレーズである。ちなみに抱いている子どもはピカソとマリー=テレーズの間の子どもで、隣の牛(ミノトール)はピカソ自身を表している。この時期、ピカソは自分自身の象徴するものとして、それまでの道化師からミノトールに移り変わっていた。


ドラ・マールの写真から影響
写真家のドラ・マールは1936年からピカソと制作をしてきた女性で、当時のピカソの愛人でもあった。マールはピカソのスタジオで「ゲルニカ」の制作過程の写真を撮りつつ、時には製作中のピカソもカメラに収めた。
また、カメラを用いず印画紙の上に直接物を置いて感光させる「フォトグラム」の手法をピカソに教えたりもしていた。
マールの白黒写真の撮影テクニックはピカソのゲルニカ制作において影響を与えた。ゲルニカがモノトーン一色であるのは、モノトーンが生み出す即時性効果やインパクトを作品に与えるためだった。また、ピカソがゲルニカ爆撃の写真を初めてみたときにショックを受けたのが白黒カラー報道写真だったともいわれ、報道的な側面を強調したかったと思われる。
そのためこの作品は、ピカソの要求に応じて特別に調合された艶消し塗料を使用して塗られています。同様の手法は1951年に描いた『朝鮮の虐殺』でも採用されています。

<参考文献>