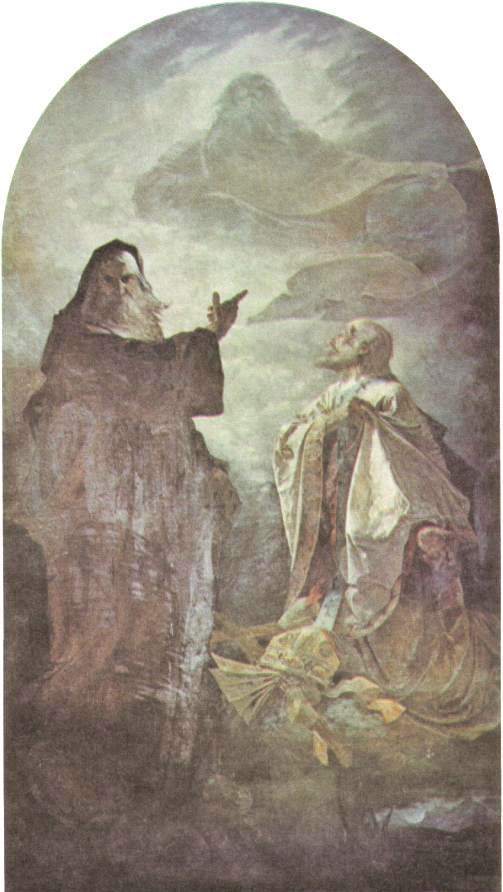カウズ / Kaws
ストリート・ファッションとアートの融合

概要
| 生年月日 | 1974年11月4日 |
| 住居 | ニューヨーク |
| 国籍 | アメリカ |
| 表現形式 | 絵画、彫刻、グラフィックデザイン、ストリート・アート、トイ |
| 公式サイト | https://kawsone.com |

ブライアン・ドネリー(1974年11月4日生まれ)、通称Kawsは、ニューヨークを基盤にして活動している画家、グラフィック・デザイナー、彫刻家、トイ作家、ファッションデザイナー、グラフィティ・アーティスト。
Kawsの作品では同じ具象的なキャラクターやモチーフが繰り返し使われる。それらの多くは彼の初期キャリアである1990年代初頭に創造したもので、当初は平面で描かれていたが、のちに立体に発展した。
Kawsのキャラクターの中にはオリジナルのものと、他のクリエイターのキャラクターをリメイクしたものがあり、数インチの小さなものから10メートル以上に及ぶ巨大なものまでサイズはさまざま。さらに、状況に応じて、アルミニウム、木、ブロンズなどさまざまな素材が使われている。
現在、Kawsはニューヨークのブルックリンを拠点にして作品を制作しつつ、パリ、ロンドン、ベルリン、台湾、東京など世界中に足を伸ばして活動を行っている。
Kawsの作品は現代美術だけでなく一般庶民層まで幅広く認知されている。アート・マイアミ2019期間中に会場内で撮影されてInstagramにアップロードされた作品を解析すると、Kawsが最も多かったという。
Kawsの作品はアトランタのハイ美術館、フォートワース現代美術館、パリのローザンブラム・コレクションで鑑賞することができる。

略歴
若齢期
Kawsはニュージャージ州のジャージーシティで生まれた。本名ブライアン・ドネリー。1996年にニューヨークのマンハッタンにあるニューヨーク美術学校(School of Visual Arts)イラストレーション科の学士を得て卒業。
その後、フリーランスのアニメーターとしてディズニーで働く。『101匹わんちゃん』や『ダリア』『ダグ』などのTVアニメシリーズの制作に携わる。
グラフィティ・アーティストとしてのキャリアは、子ども時代にジャージーシティで育ったときから始まっていry。1990年代初頭にニューヨークに移ったあと、本格的に活動をはじめる。壁や貨物列車に「Kaws」と名前を書き残し、グラフィティ・アーティストとして活躍しはじめる。このころに、のちに自身のトレードマークとなる、二本の骨が交差し、目が×印のソフトな印象のスカルマークを創造したという。
また、バスの待合所や電話ブースにある広告を書きかえはじめる(subvertising)。これら書き換えられた広告は最初そのまま放置され、数ヶ月間そのままの状態になっていたという。しかし、Kawsの知名度が上がるにつれて、広告は書き換えられたあと、すぐに探され盗まれるようになった。
Kawsは、アメリカだけでなく、パリ、東京、ロンドン、ベルリンなど世界中で書き換え行為を行っている。
キャリアを積み重ねていくにつれ、ゲルハルト・リヒターやクレス・オルデンバーグ、チャック・クローズといったファインアートの画家から影響を受けるようになり、現在のKawsは彫刻、アクリル画、シルクスクリーン作品なども制作している。
また、企業とのコラボレーション活動にも積極的で、限定版トイやファッション、スケートボードなどさまざまな製品を制作している。
作品
Kawsのアクリル画や彫刻では、繰り返し同じイメージが使われており、それらは言語や文化を超えて世界的に受け入れられている。彼のキャラクターの源泉は1990年初頭の初期キャリアまでさかのぼる。
『コンパニオン』『アコンプリス』『チャムとベンディ』といったよく知られているキャラクターは、Kawsの初期キャリアの1つである。『パッケージ・ペインティング』シリーズは2000年に制作された。『ザ・キンプソン』シリーズはアメリカのカートゥーン『ザ・シンプソンズ』を書き換えた作品である。
Kawsは「人々の生活の中に漫画がどのように入り込んでいるか不気味にかんじた。その衝撃は習慣的な政治と比較するほどのものだ」と話している。追加すると、Kawsはミッキー・マウスやミシュランマン、スヌーピー、スポンジ・ボブなどのキャラクターを書き換えた作品も制作している。
1999年以来、Kawsは定期的にパリのコレットで絵画とプロダクトの両方の展示を続けている。
Kawsの展覧会では、オハイオ現代美術館からはじまり全米やヨーロッパを巡回した『Beautiful Losers』や、2012年にジョージア州アトランタのハイ美術館で開催された当時最大の美術館におけるショーなどがよく知られている。
顔を両手で覆い隠したミッキー。マウスの基盤にしたグレイ色のピエロのようなキャラクターの『コンパニオン:は、2012年のメイシーズ・サンクスギヴィング・デイ・パレードで巨大風船として使われた。
企業とのコラボレーション
1999年にKawsはプロダクト・デザインの仕事をはじめる。日本のアパレルブランド『バウンティー・ハンター』と共同で限定版ビニールトイの制作をはじめ、世界的にヒット。
ほかにも、『ア・ベイシング・エイプ』『サンタスティック!』『メディコム・トイ』など、多くの日本のアパレルブランドとコラボレーション活動をしている。
また、メディコム・トイとの共同プロジェクトブランドである『オリジナルフェイク』を立ち上げ、東京の青山を拠点にし、おもちゃやファッションの生産を始める。同ブランドは創立7周年となる2013年5月をもってクローズした。
2013年の『MTVビデオミュージック賞』で、KAWS会社は、月面旅行者を模したデザインを発表、また『The New Yorker』『Clark Magazine』『I-D』などさまざまな雑誌カバーのデザインを行なった。ほかには、トワ・テイ、ザ・クリプス、カニエ・ウェストなどミュージシャンのカバーアートも行なった。
2014年にKAWSは長年の親友であるファレル・ウィリアムスと、コム・デ・ギャルソンの香水『Girl』のボトルデザインのコラボレーションを行う。
2016年にKawsはユニクロとコラボレーションを行い「UT」として、Tシャツやアクセサリーを販売し、世界中で大ヒットとなった。さらに、2018年11月には世界中で大人気のテレビ番組「SESAME STREET(セサミストリート)」とのコラボレーション「KAWS × SESAME STREET」としてスペシャルコレクションをユニクロから発売した。
2017年5月、ニューヨーク近代美術館は200ドルのKaws限定アクションフィギュアを発売。また、イギリスのオークションハウス、フィリップスで2011年に制作したKawsのブロンズ製『コンパニオン』が41万1000ドルで落札された。
2019年6月、中国でUNIQLO x KAWSのコラボTシャツの争奪をめぐる大規模争奪騒動が発生。アリババのECサイトで商品の販売が始まったが、瞬く間に売り切れになったあと、翌朝の実店舗に広がる。実店舗にオープン前から客が集まり、開店と同時になだれ込み商品の争奪合戦が繰り広げられた。
商品
2019年 KAWSサマーTシャツ販売開始
夏にぴったりの、カウズのオリジナル作品がUTにカムバック
代表的なキャラクターである「COMPANION」や、青やピンクのボディが印象的な「BFF」が、シンプルながら魅力的にデザインされています。 袖には、トレードマークの「XX」がひっそりあしらわれ、カウズの世界観を存分に味わえるコレクションに仕上がりました。
楽天ショップ
UT ユニクロ KAWSポケット付きTシャツ
|
|
|
|
KAWS×メディコムトイ フィギュア
|
|
■参考文献
・https://en.wikipedia.org/wiki/Kaws 2019年2月11日
■画像引用
※1:https://en.wikipedia.org/wiki/Kaws 2019年2月11日
※2:https://en.wikipedia.org/wiki/Kaws 2019年2月11日

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1896225f.b46662b6.18962260.acbdb3b5/?me_id=1222711&item_id=10043217&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famaxshop%2Fcabinet%2F1664%2Fx180920005.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Famaxshop%2Fcabinet%2F1664%2Fx180920005.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)