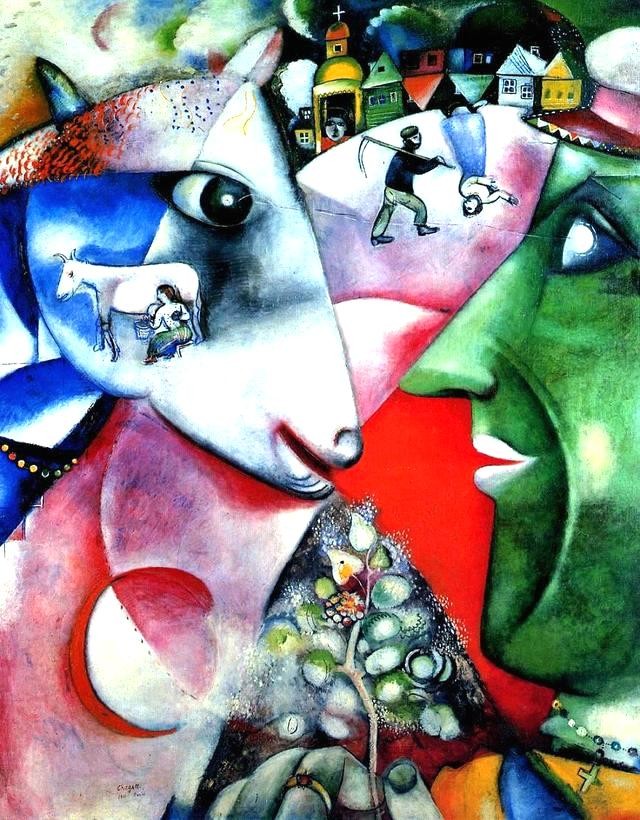泉 / Fountain
20世紀美術のランドマーク作品

概要
20世紀最大のランドマーク作品
「泉」は1917年にマルセル・デュシャンによって制作されたレディ・メイド作品。セラミック製の男性用小便器に“R.Mutt"という署名と年号が入れられ、「Fountain」というタイトルが付けられている。このタイトルはジョゼフ・ステラとウォルター・アレンズバーグが決めたといわれている。
1917年にニューヨークのグランド・セントラル・パレスで開催された独立美術協会の年次企画展覧会に出品予定の作品だったものである。この展覧会では手数料さえ払えば誰でも作品を出品できたにも関わらず、「泉」は委員会から展示を拒否される。その後、作品はアルフレッド・スティーグリッツの画廊「291」で展示され、撮影され、また雑誌『ザ・ブラインド・マン』で掲載され批評が行われたが、オリジナル作品は消失。
1960年代にデュシャンの委託によって17点のレプリカが作られ現存している。本作は前衛芸術の美術史家でまた理論家であるピーター・バーガーにより、「泉」は20世紀の前衛美術の最も主要なランドマーク作品としてみなされている。
制作と展示まで
マルセル・デュシャンは「泉」を制作する2年前にアメリカへ移住し、ニューヨーク・ダダムーブメントの中心人物として活動していました。
「泉」の制作には2つの説があります。デュシャンはニューヨーク五番街の衛生器具店「J.L.モット・アイロン・ワークス」で標準的なベッドフォードシャー・モデルの男性用小便器を購入し、西67番街にあるスタジオに持ち帰ったあと、通常の使用位置から90度傾けて、排水口の部分が正面に来るようにして、正面に "R. Mutt 1917"と署名したという制作過程です。また、「泉」の制作には、画家のジョセフ・ステラやコレクターのウォルター・アレンズバーグも関与したとされています。これが、一般的に広く浸透している説です。
もう1つは「泉」の作者はデュシャンではないという説。本来は独立美術協会に出品予定だった女性アーティストとの友達の作品を手助けしたものだったといいます。1917年4月11日付けの妹シュザンヌに宛てた手紙でデュシャンは、泉の出品に関する事を書いています。そこには「「リチャード・マット」という男性のペンネームを使って、私の友人の一人が私に彫刻作品として送ってきた」と記載されています。
デュシャン決して協力した人物を公表することはありませんでしたが、現在2人の人物が真の作者として考えられています。1人は同じニューヨークの女性ダダイストのエルザ・フォン・フライターク・ローリンホーヴェンで、彼女の美術的価値や作品はデュシャンのレディ・メイドと極めて似通っています。
もう一人はルイズ・ノートンで、彼女は『ブラインド・マン』誌上に泉に関する解説文を執筆したとされる人物です。ルイズ・ノートンは当時、夫と離婚して両親とニューヨーク西88番街のアパートに住んでいましたが、この住所はスティーグリッツの写真で見られるが、オブジェに付いている入場券の紙に記載されている住所と同じのようです。
展示委員は送られてきた「泉」を会場の仕切りの裏に置いて、カタログにも掲載しませんでした。デュシャンはこのことに抗議して、展覧会の委員を辞任。この一連の出来事を「リチャード・マット事件」といいます。
現在、写真で残っているオリジナルの「泉」は、アルフレッド・スティーグリッツのスタジオで展示されて撮影されたもので、雑誌『ザ・ブラインド・マン』に掲載されたものですが、オンライン・ジャーナルの「Tout-Fait」上で記者のロンダ・ローランド・シアラーは、スティーグリッツが撮影したとされる「泉」の写真は異なる写真の合成であると指摘しています。
展覧会が終了したあと、オリジナルの「泉」は消失。デュシャンの伝記作家のカルヴィン・トムキンスは、デュシャンの初期レディメイド作品と同じくスティーグリッツがゴミとして廃棄したと書いています。
1950年のニューヨークの展示の際に初めて、デュシャン公認で「泉」のレプリカが制作されました。1953年と1963年にさらに2つの作品が制作され、その後、1964年には8個のレプリカが作られました。これらレプリカ作品は、インディアナ大学ブルーミトン、サンフランシスコ近代美術館、カナダ国立美術館、テート・モダン、パリ・ポンピドゥー・センターなどに収蔵されています。
レディ・メイドの制作意図
また、1917年5月に、雑誌『ザ・ブラインド・マン』の第2号でデュシャンは匿名で抗議文を投稿し、そこに「泉」の作品意図を寄稿しています(この文章を書いたのがルイズ・ノートンと見られています)。『ザ・ブラインド・マン』とはアンリ=ピエール・ロシェ、ベアトリス・ウッドと発行していた雑誌でダダイスムの情報誌のようなものでした。雑誌では次のような抗議文が匿名で掲載されました。
「リチャード・マット事件。6ドルの出品料を払った作家は誰でも出品できるという。リチャード・マット氏は「泉」を送った。この品物は間違いなく消え失せ、金輪際陳列されなかった。マット氏の「泉」を拒否する根拠は何であったか。
(1)ある連中はそれが不道徳で卑俗だと主張した。
(2)別の連中はそれが剽窃であり、たんなる衛生器具にすぎないと主張した。
さて、マット氏の「泉」は不道徳ではない。そんなことはばかげている。浴槽が不道徳でないのと同じだ。それは衛生器具屋のショー・ウインドウで毎日見かける設備である。マット氏が「泉」を自分の手でつくったかどうかは重要ではない。彼はそれを選んだのである。彼は生活の中の日常的な品物をとりあげ、新しい題名と新しい観点のもとでその有用な意味が消え去るように、それを置いたのである。つまり、あの物体に対する新しい思考を創り出したのだ。衛生器具云々というのはまったくお笑いぐさである。アメリカが生み出した芸術品といえば、衛生器具と橋だけではないか」
この抗議文を書いたのはデュシャンとされていますが、実際はルイーズ・ノートン、ベアトリス・ウッドなど当時の編集スタッフらで書かれたものと考えられています。ただし、デュシャンのレディメイドの意図に関してははっきりと表明されています。
レディ・メイドの意図は以下の3点になります。
- 「ハンドメイド」より「選択という行為」
- 日常的な機能の剥奪
- 新しい思考の創造
●コンセプチュアル・アート
デュシャンは泉の制作について、まず趣味という問題を試験してみるところから生まれたと話しています。デュシャンの趣味というのは「視覚的に無関心」なオブジェでした。全く人の気をひかないものを選ぶというのがデュシャンの趣味で、その延長で男性小便器が選択されました。
「わたしの”泉”=”便器”は、趣味という問題を試験するという考えから生まれた。つまり、全く好かれそうもないものを選ぶということだった。便器を素晴らしいと思う人は、およそ、いないだろう。つまり危険なのは「芸術(アート)」という言葉なのだ。「芸術」といえば、本当は、なんだって芸術を思わせることができるのだ。それで、レディ・メイドとして選択されるオブジェのポイントは、私にとって視覚的に魅力的でないオブジェを選ぶことでした。選択するオブジェ対象は、「見かけ」が私にとって無関心であることでした。(マルセル・デュシャン)」
こうした意図のもと、普段見ているモノに対して「新しい思考」の創出をデュシャン提示しました。この考え方は後にコンセプチャル・アートやポストモダンアートにつながっていき、このデュシャンの「新しい思考」の創出というのが現代美術の基本的なルールになります。芸術の概念を「物質的な工芸(ハンドメイド)」から「知的な解釈」に変えるとともに、「選択」という行為が重要になりました。
●ポップ・アート
デュシャンは本来であれば有用であるものを選びました。その代表が日常的品物でした。日常的品物で本来は有用である便器をとりあげ、新しい題名「泉」と新しい視点のもとで本来の意味を消え去るように展示したというのです。
「便器を日常の文脈から引き離して、芸術という文脈にそれを持ち込んで作品化したこと」が重要なのです。この考え方は、シュルレアリスムのコラージュやポップ・アートと同じものとおもえばいいでしょう。
コラージュは、雑誌から切り抜いた素材を使って新しい視覚芸術を創造するための錬金術といわれます。ポップ・アートもまた新聞、雑誌、広告、写真など身近な大衆メディアや日用品を活用したことで「これが芸術?」というような文脈から現れました。レディ・メイドも同じです。
そのほか
●匿名芸術
「泉」はまた、美術の作者は美術家ではなく鑑賞者であることを提示しました。本来「美術の作者は美術家」であり、そして鑑賞者は美術家の意図を理解するというのが常識的な見方でした。
そういった美術の古典的なルールに疑問をもったデュシャンは、大量生産された何の思想もメッセージも込められていない便器を美術展に投入しました。すると本来何もメッセージも視覚的に面白くもないはずの便器が、鑑賞者を誤読させ、解読が始まり、それについて語られ美術化されていく。そのため、デュシャンは、R. Mutt(リチャード・マット)という偽名を使って、作者の意図が分からないようにしていました。
「泉」は展示されなかったこともあり、制作関係者以外に実物を見た人はほとんどおらず、アルフレド・スティーグリッツが撮影した唯一の写真でのみ確認できます。特定の角度で映された便器をよくよく見ると、その緩やかな曲線と形から隠されたヴェールを付けたの古典絵画のマリアや座禅を組んだブッダの彫刻、ほかにブランクシーのエロチックな形態の彫刻を連想させます。
また便器を「泉」と付けた経緯ですが、泉は独身者にも置き換えられます。この小便器に向かって放尿すると、それは手前の穴から流れでて、その人自身に尿のとばっちりが及ぶことになる。これは鏡の反射を表している。満たされることのない欲望を抱えた独身者たちがそれに向かって性器を露出し、同時に、性器から放出される液体を受け止め、受け止めた液体がまた穴から戻ってくる。自己愛でありオナニズムである。
またデュシャンはこのようなメモ書きを残している。
「これしかない。雌としては公衆小便所、そしてそれで生きる。」
































































































![非現実の王国で ヘンリー・ダーガーの謎 デラックス版 [DVD]](http://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=150x10000:format=jpg/path/s093251349da78e77/image/id29fe908b08a2f8a/version/1423635797/image.jpg)